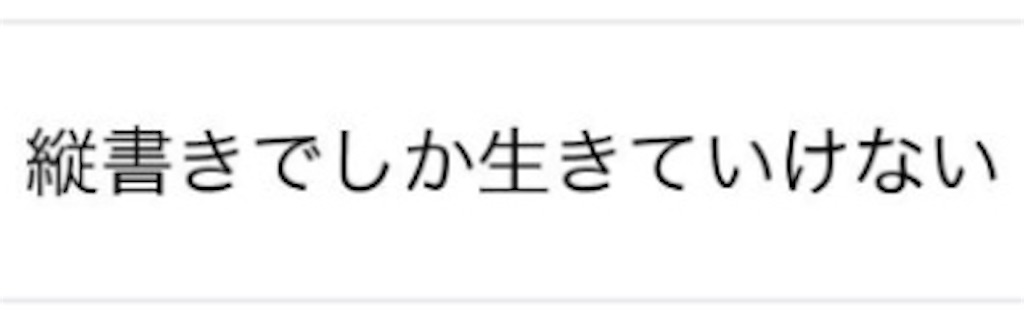縦書きでしか生きていけない
メルカリで買って届いた本を今日早速サンマルクカフェに座って読んだ。丸山圭三郎の『文化のフェティシズム』。ちょっと(かなり)古い本だけど、ソシュール研究の第一人者である丸山の思想の到達点などと紹介されていて、読まずにはいられなかった。

- 作者: 丸山圭三郎
- 出版社/メーカー: 勁草書房
- 発売日: 1984/10/15
- メディア: 単行本
- クリック: 8回
- この商品を含むブログ (9件) を見る
ソシュールは自身の思想を論文などには残していない。ソシュールが大学で行った講義で受講生が取ったメモは残っていて、思想はそこから読み解く他ない。というわけでソシュールを原文で読むというのはかなり難しい。そんな事情がなくても僕は縦書きの日本語でしか読めないけれど。
丸山圭三郎は世界に先駆けて講義メモを組み合わせて思想をまとめあげるという大仕事をした研究者だ。この人の文章は、出典や注を充実させる丁寧な研究者の文章でありながら、読み手をワクワクさせる作家のそれでもある。言葉の研究者なだけある。そういうわけですっかり気に入って、ソシュールの思想そのものはもちろんのこと、彼の言葉に飛び込んで楽しむためにこれまで『言葉とは何か』『ソシュールを読む』『ソシュールの思想』と読んできた。内容も文章も好きじゃないとなかなかいくつも読む気にはならない。大学時代に出会った中では他に河合隼雄とエーリッヒ・フロムくらいのものだ。三大好きな文章家の一人というわけ。
実際に彼の著書を読んだのは大学3年のころだった。それが今になって彼の文章への熱が再燃したのは、仕事で(教える/学ぶ)を考える上で、ソシュールの理解を深めることが、ひとつのブレイクスルーにつながるような直観があったからだ。そこでまずは『言葉とは何か』を読み返した(読み返そうと思ったら家で見つからなかったので買い直して読んだ)。短い新書だからあっという間に読み終えて、やはり言葉について考えねばならないという気持をつよめた。

- 作者: 丸山圭三郎
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2008/04/09
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 11回
- この商品を含むブログ (25件) を見る
高ぶっているところで読んだあとがきに丸山の弟子が『文化のフェティシズム』について、
丸山によるソシュール解釈の最高到達点であると同時に、丸山理論の積極的な展開の始まりとなった書物。
などと書いていたものだから、すぐに検索して買ってしまった。2日前のことである。今のところ数十ページ読んでみて、買ってよかったと言う他ない。
…
直観といっても、その予兆はいくらでもあった。仕事でプログラミングを教える。とかく初学者への解説は根気が要って、相手の理解度を図りながら、言葉づかいだの図の書き方だのどうすればわかってもらえるのか工夫しようと考えだせば底がない。そんな中で得た直観のひとつは『教える上では、「なぜ分からないのか?」より「なぜ分かるようになったのか?」を問うほうがよい』ということだ。これは仕事仲間と話しているうちに不意に自分の口をついて出た言葉でもある。自分の言葉に、なるほどそのとおりだと思った。このように問いを変えると、質問の相手が他人ではなく自分自身になる(そういえば誰かが汝自身を知れって言ってたな)。これでぐっと身近になる。どこから手を付けていいかわからない、何が問いかさえよくわからない難題に手がかりを見つけた。
自分自身に問うとは、ひとつには自分の過去を振り返ることである。「自分はいかにして分かってきたか?」しかしこれは過去に意識したことがなければ答えを出すのが難しい問いである。
あるいは、自分の現在を分析することである。「自分はいかにして分かりつつあるか?」「自分はいかにして分かろうとしているか?」今すぐ答えが出るわけではないが、これを継続して問うことは非常に実りあることのように思う。いまのところ自分自身の蓄えがないので、現在の自分を見つめることは分析の視点の一つというには程遠く、せいぜい問いへの姿勢でしかない。
もうひとつは、人間の本性を暴くことである。「人はいかにして分かるのか?」この問いに答えるのは、僕の場合発達心理学だった。大学では卒業に必要な学科の単位はそっちのけで他の学科の授業をとっていて、そのひとつに発達心理学の講義があった。赤ちゃんがいかに発達するかを研究する学問である。これを思い出し、体系を学ぶということ、外界の認識、人間が言葉を学ぶ過程とプログラムの実行の類似性とか(これについては改めて考えてみたい)、おいしいヒントが転がっていることに気づいた。あの学期で一番興味を持って聴いた講義だったし(建築学科の講義はひとつも面白くなかった)、いまもこうして学びを得ている。みんなも騙されたと思って受講してみよう。

- 作者: 今井むつみ
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2013/01/09
- メディア: 新書
- 購入: 4人 クリック: 11回
- この商品を含むブログ (16件) を見る
ここまでの経緯をつらつらと書いてしまったが、僕自身これが本当に自分に起きたこととは思えない。直観にかかわる因果を、直観に至るまでの・至ったあとの出来事を時系列に乗せて述べるのは難しい。「なんか違う」とは思いつつも、一旦書き始めてしまったから書いただけ。すべてが関係しあっている。思いつくより先にわかっていたような気もするし、わかっているようでわかっていない気もする。いつからそう思ったのか、なぜそう思ったのかもわからない。ソシュール自体もともと好きで、発達心理学の第一回講義のときにこれはソシュールだ!と思って興味が湧いた、しかしなぜ好きだったのかというとよくわからない。講義や本と一緒に知らず知らず飲み込んだ種が腹の中でようやく芽吹いて、僕が「分かるということ」について考えずにはいられないよう内側からくすぐっているかのようだ。僕は何かをわかろうとして、つまり内なる目的のために講義を受けていたのでも本を読んでいたのでもない。しかし事実としていま僕は自分の口に手を突っ込んで、数年もののその実を取り出そうとしている。こんなことになるとはと思いつつ。確かなのは、そんなこんな生きているうちに、自分の「分かる」の大本にソシュール的思想があると思うようになったという感覚だけである。
…
今は、教えるにしろ学ぶにしろ、理解の仕組みを知ることでより効果的に行えるに違いないと考えている。さらに「あらゆる学びの対象は体系という性質を持つ(言葉が体系である以上、そこから生まれる一切は体系である)」ことからスタートして体系の本性を探っていけば、なにかすぐそこにヒントが得られるような気がしている。そのために、しばらくはソシュールと丸山の冒険の軌跡をたどってみたい。
ソシュールの言う《体系》の概念は、それまで使われていた体系と根本的に異なります。従来の体系というのは、既成の事物がどう配置されどう関係づけられているかという表なのですが、ソシュールの場合には、もともと単位 unité という客観的実体は存在しないというまことに不思議な体系を考えています。その体系の中では、個々の単位の大きさとか価値 valeur はネガティブにしか定義されない、と言うことができるでしょう。(中略)存在するものは隣接する他の諸項と、全体との、二つの関係だけから生れる大きさでしかありません。(『言葉とは何か』p132-133)
サンマルクカフェにて、精緻な分析と密度の高い文章にすっかり引き込まれてしまった。
読みながらザッとまとめた文化のフェティシズムの序章のメモを貼っておく。彼がソシュールに出会うまでに感じていた現実不信感などは非常に共感することが多く、ソシュールに触れたときの静かな衝撃はひしひしと伝わってくる。これを読んだ人にも輝くばかりの原文を読んで、一緒に丸山青年の知的興奮にあてられてほしいけど…。
…
胡蝶の夢 ―序に代えて―
丸山は小学生のころより大学生に至るまで、様々な読書体験をし、その都度次のような感覚を抱いていたという。
「月と雲」から太宰治を経てJ・グリーンへとのめりこむ過程は、一貫して「何故」を問うても答えのない現実不信、現実気迫感であった。
その後丸山はひょんなことからソシュールに出会い、衝撃を受ける。
(前略)ソシュールの手稿9に見出した次の文はまことに衝撃的であった。
事物そのものに先立って事物と事物のあいだの関係が存在し、その関係がこれら事物を決定する役割を果す。(……)いかなる事物も、いかなる対象も、一瞬たりとも即時的には与えられていない。
これを読んだ私には、従来の観念論、実在論がともに疑ってみようともしなかった<ロゴスの現前>が、ソシュールによって根柢から覆えされたと思えた。文化現象の一切は表象によって二次的に生み出された共同幻想の世界で、その表象すらももともとは存在しなかった関係の網の目に過ぎない、という考え方は、ヘレニズム、ヘブライズムの正嫡である西洋近代思想をその根源から揺さぶる。絶対的神も理性も世界の理法もア・プリオリではない。この視点に立ってはじめて、従来は非合理ということで学問の対象とは認められなかった無意識とか夢とか狂気、観念の名のもとに隠されていた身体性、あるいは身体性のそこにある欲動の世界が照射されるのではあるまいか。
ここに引用されているソシュールの言は彼の思想の中心であり、今後の議論を理解する上で非常に重要な概念である。
そして何よりもまず、この思想家の考え方は<アニマル・シンボリクム animal symbolicum>としての人間文化の病状告発にとどまらず、その原因の診断に、つまりは「何故」の問題に立ち入ることを可能にしてくれるように思われたのである。
患者自身による病気の告発、医師による診断、治療という一般的な流れが、我々を覆う様々な<文化の病い>にも重なることを言い、その上で当時の思想界を
一方にやたらと病状告発に精を出す論者がいるとすれば、他方には請求に処方箋を求める読者がいるように思われる
と断ずる。 丸山が飲み込んだソシュールの思想は、思想界の無益なすれ違いからみなの目を覚まさせる強力な武器になった。ソシュールの見方でもって現象を理解しようという過程自体が、様々の問題の解決に至る道なのではないかと信じて。
本書は、<処方箋なき診断>が果たして<治療>の一歩となり得るかどうかを探る一つの試みにほかならない。